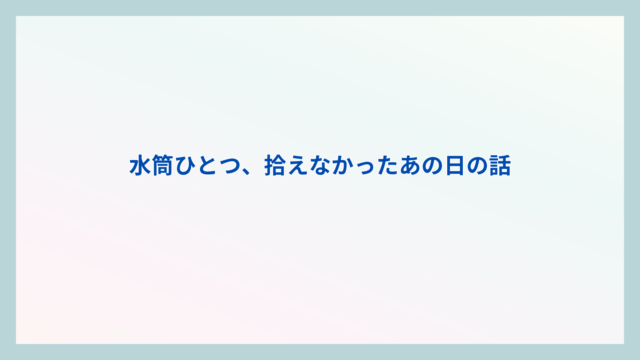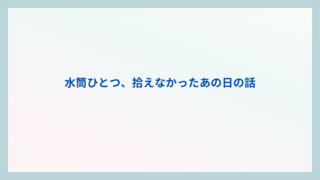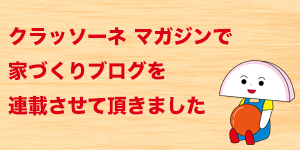真夜中の麦茶がなぜか最高にうまかった件

夜中、なんだか喉が渇いて目が覚めた。冷蔵庫を開けると、麦茶のポットが目に入る。コップに注いでぐいっと飲むと、これがまたうまい。身体の芯にじわりと染みていくような感覚。エアコンで乾いた喉にちょうどいいぬるさで、なんとも言えない安心感があった。たかが麦茶、されど麦茶。ふと、昔のことを思い出した——そう、高校時代のあの寮生活の夜のことだ。
あれは、今思えば相当にヘンテコな学校のイベントだった。1年生のときに1週間ほどの「寮生活体験」なるものがあって、クラス単位で学校所有(かどうかは曖昧)の山奥の寮に放り込まれるのだ。今ならSNSでバズって炎上してそうなレベルの強制合宿(ではないか)。
しかもその寮というのが、なんというか、昭和というより戦前の雰囲気で、木造の軋む廊下に、虫の侵入を防げる気配のない障子窓。洗面所には割れた鏡がそのまま放置されていて、夜になるとそこに映る自分の顔がホラーより怖い。
「まずバルサンを炊け」というのが先輩からの教えだった。到着してすぐに荷物を下ろす間もなく、各部屋でバルサンを焚いて避難。その煙の充満した部屋を見て、なぜかテンションが上がる。男子高校生ってのは、煙とか火とか爆発音に異様に惹かれる生き物なのだ。
昼間は普通に授業に出て帰ってきたら自習の時間があった。夜は決まった時間に寝なさいというお達し。だけどそんなルールをまともに守るような奴はクラスに数人くらいしかいなかった。むしろ、それをどう破るかに知恵を絞るのが高校生男子の正しいあり方だった気がする。
その夜だった。たまたま隣の布団で寝ていたA君が、ひそひそ声で話しかけてきた。「なあ、喉乾かん?」「乾く」「麦茶、飲みたくない?」「飲みたい」──即決だった。
もちろん、寮内は消灯後に部屋から出ていいのはトイレのみとされていた。だが、そんなルールは、夜の喉の渇きには勝てない。二人で布団から抜け出して、そろりそろりと廊下を歩いた。夏の夜、畳の冷たさが足裏に心地よい。まるで忍者のように物音を立てず、階段を下りる。
食堂にたどり着いた瞬間、ぼくらは視線を交わし、にやりと笑った。冷蔵庫は鍵がかかっていなかった。中にはジャグポットに入った麦茶がぽつんと置かれているだけ。おそらく教師用だったのだろう。だが、そのときのぼくらにはそれがまるで金の壺に見えた。
紙コップに麦茶を注いで、一気に飲む。ごくごく、ぷはー!……その瞬間、ぼくとA君は、何とも言えない幸福感に包まれた。ふたりで飲む夜の麦茶。たったそれだけなのに、心の底から笑いがこみ上げてきた。口を開けると笑い声が漏れそうで、口を押さえながら肩を震わせた。
この出来事、今の感覚で言えば「なんてことない」し、SNSで言えば「映えない」。だけど、あの夜、ぼくらは間違いなく冒険していた。隠れて抜け出すスリル、ふたりだけの秘密、そして麦茶の味。全てが一瞬にして心に刻み込まれた。
その後、ふたりで「絶対にバレないように戻ろう」と言いながら、同じルートで部屋に戻った。布団に戻ると、まだ口元が緩んでいた。A君が小声で「また明日も行こうぜ」と言ったが、翌日は全員にあらためて外出禁止の通達があり、完全に気配を読まれていたことを後で知る。やっぱり先生はベテランだ。
あれから何年も経ったけれど、夜中にふと麦茶を飲んだだけで、あの夜のことを鮮明に思い出す。あのときの麦茶の味、湿った廊下の匂い、A君と顔を見合わせたときのくだらない達成感。全部がまるっとパックになって、記憶の冷蔵庫にしまわれていたんだなあ、と思う。
今のぼくは、大人としてのいろんな義務や責任を背負って生きている(そうでもないか…)。麦茶を飲むだけで笑い転げるなんてことは、まあない。そもそも、深夜に忍び足で何かするような機会も減った。代わりに、子どもたちの夜泣きで目を覚まし、水やおむつを手にうろうろしている毎日。そういう生活も悪くないけれど、ときどきふと、あの夜のことを思い出すのだ。
もしかすると、あのときの麦茶の味っていうのは、味そのものよりも、あの時間と空気と、共犯者がいたことが何よりのスパイスだったのかもしれない。だから今飲んでも、同じ味にはならない。けれど、その「違い」があるからこそ、あのときの「特別さ」がちゃんと今も輝いている気がする。
A君とは今、頻繁なやりとりは途絶えてしまった。あの頃みたいにこっそりとはいかないけれど、大人になったぼくらが今度はビール片手に、夜の縁側で麦茶の話をするのも悪くないと思う。
あの夜の麦茶は、今でもぼくの中で「あそこでしか飲めない麦茶」として、燦然と輝いている。